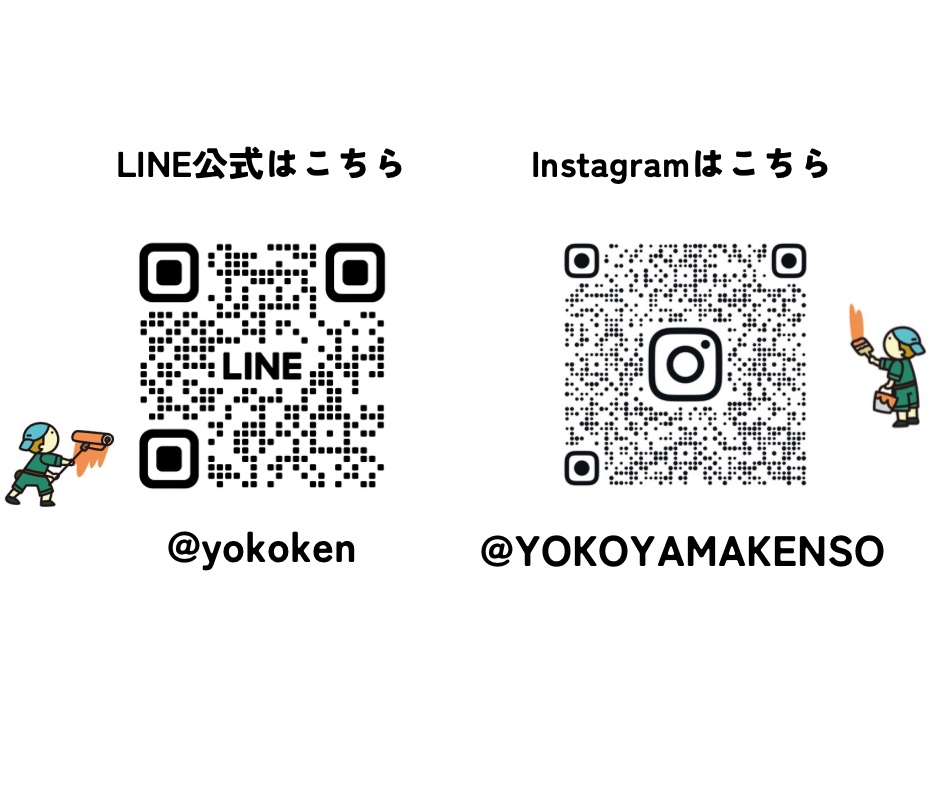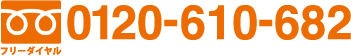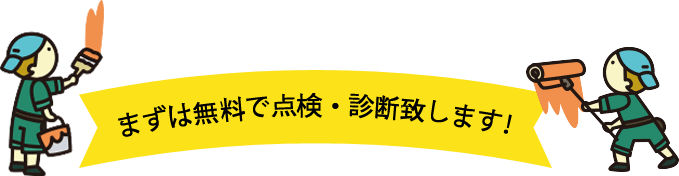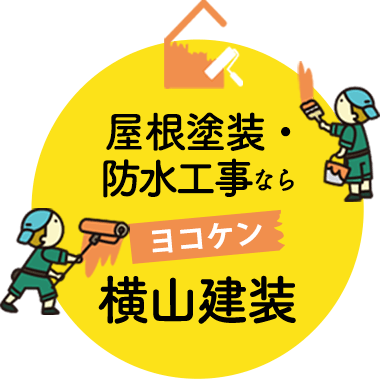
スタッフブログ
日本の住宅でよくある雨漏りパターン 大府市・東浦町・東海市で屋根塗装・屋上防水工事なら横山建装
日本の住宅でよくある雨漏りパターン
2025.11.20
今回は「日本の住宅で雨漏りが起きやすいパターン」を、築年数別にわかりやすくまとめました。
築年数ごとの注意ポイントを知っておけば、定期メンテナンスや点検のタイミングが分かりやすくなりますので参考にしてくださいね。
雨漏りは築年数によってリスクが変わる?
まず押さえておきたいのは、雨漏りは 年数が経つにつれて起きやすくなる傾向があるということです。
というのも、屋根材・防水層・シーリング(コーキング)など、時間とともに劣化する部分が多いためです。
築年数別・雨漏りリスクの特徴
築0~10年(比較的新しい住宅)
- 主な原因:施工不良や設計ミス
- 防水シート・ルーフィングの施工が甘いと、最初のうちから雨が入り込むことがある。
- 窓・サッシまわりのシーリング(コーキング)が不十分だと、隙間から浸水。
築10~30年(メンテナンスが重要になってくる時期)
- 主な原因:経年劣化
- スレートや瓦など屋根材が少しずつ劣化し、ヒビやカケが出てくる。
- 外壁・サッシのシーリングが紫外線・温度差で硬くなり、防水性が落ちて隙間ができてくる。
- ベランダ・屋上の防水層(ウレタンやFRPなど)の寿命が10~15年あたりで切れ始める。
- 雨樋(どい)がゴミで詰まる、あるいは破損して排水が悪くなる → 雨水が外壁を伝って浸水。
築30年以上(古めの住宅)
- 主な原因:老朽化がかなり進んでいる
- 建物自体が歪んだり、下地に隙間が出てきて雨が入りやすくなる。
- 屋根材の劣化が広範囲に及んで、雨漏りが慢性的なものになるケースも。
- 防水層が寿命を迎えている可能性が高く、全面的な防水改修が必要になる。
- 雨樋・排水部分の老朽化で、水の逃げ場がなくなり浸水リスク増。
なぜ年数が進むと雨漏りしやすくなるの?
- 材料劣化が進む
- シーリング剤(コーキング)は紫外線や気温差で劣化しやすく、10年~15年で性能が落ちる。
- 防水シートや屋根材も、長年の雨・紫外線・風で傷みが出る。
- 設計・施工の弱点
- ドレン(排水口)まわりや取り合い部(屋根と壁、窓など)が構造的に雨水侵入リスクが高い。
- 自然のダメージ
- 台風・大雨・雪などが、年を経て建物にダメージを与える。
- メンテナンス不足
- 点検を怠ると、小さな劣化が見過ごされて大きな雨漏りに発展する。
4. 雨漏りを予防・早期発見するためのアドバイス
- 定期点検を習慣にしよう
- 10年を超えたら、屋根と防水層、シーリング材を業者にチェックしてもらう。
- セルフチェックも大事
- 天井・壁にシミがないか、窓まわりのコーキングがひび割れてないかを定期的に確認。
- 雨樋にゴミが詰まっていないかを見て、落ち葉や泥があれば掃除。
- 気になる部分は早めに補修
- 小さな隙間・傷でも放置せず、コーキングの打ち直しや部分補修を。
- ベランダ・屋上の防水層は、耐用年数(10~15年)を意識して再施工を検討。
- 信頼できる業者を選ぶ
- 過去の施工実績や保証内容を確認。
- 総合診断を出してくれる業者なら、将来的な雨漏りリスクも評価できる。
いかがでしたでしょうか。
大きな雨漏りとなる前に、セルフチェックや定期点検を行い、大切なお家を守りましょう!
東浦町・大府市・東海市で何かお困りごとがございましたら、なんでも横山建装へご相談くださいませ。